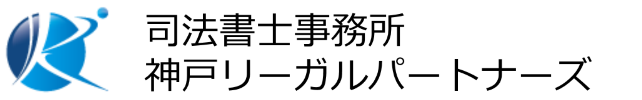相続手続きで相続人の中に海外に在住している人がいることも珍しくなくなってきました。中には、相続人が外国籍を取得して、日本の国籍を喪失している場合もあります。
日本国内の財産に関する相続手続で、相続人の中に海外在住者がいる場合は、その方は日本の印鑑証明書や住民票が発行されないので、日本在住の相続人とは異なる書類を準備する必要があります。
また、相続人全員が海外在住の場合や、日本にいる相続人が手続きを進められない場合など、海外から日本の相続手続きをどのように進めるか、誰が主導して相続手続を進めるのかといったことも考える必要があります。
ここでは、相続人が海外在住の場合の日本国内の相続手続きについて、必要書類や注意点を詳しく説明をします。
被相続人が外国籍の場合「外国人の方の相続手続き」も合わせてお読みください。
目次
2024年施行 相続登記申請義務化について
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。この相続登記の申請義務は、外国に居住している相続人も例外ではありません。
正当な理由なく相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。実際に過料が科されるのは限られていますが、義務であることに変わりありません。放置しないで早めに相続登記を申請するようにしましょう。
特に海外在住の相続人がいる場合、書類の準備や国際的なやり取りに時間がかかるため、この3年という期限を守るためには、早期の対応が極めて重要です。相続が発生したら、速やかに専門家にご相談されることを強くお勧めします。
海外在住の相続人を外して手続きしたい
海外在住者がいると相続手続きが大変なので海外在住の相続人を相続手続きから外して手続きを進めようとすることもあるようです。しかし、遺言がある場合は別ですが、そうでなければ相続人全員で遺産分割協議をして相続手続きを行う必要があります。海外在住者を除外して遺産分割協議をしても、その協議は無効で、その遺産分割協議書に従って相続手続きを進めることはできません。
また、海外在住者の行方がわからないというケースもあります。このような場合でも、行方不明の相続人を除外することはできず、場合によっては家庭裁判所で不在者財産管理人の選任が必要になることもあります。
海外在住者が手続きから外れたい
海外在住の相続人が何も相続したくないというケースもあります。
日本に帰るつもりはないので、または海外に行って日本の親戚とは疎遠だったのでといったような理由で、日本の財産は日本にいる相続人の方に相続してもらえば良いと考えているような場合です。このような場合には、海外在住の相続人が相続放棄をして、日本の相続人だけで相続手続きを進めることもあります。
ただし、相続放棄によって相続関係が変わって却って相続手続きが面倒になることもありますので、相続放棄をする際は必ず専門家に相談してください。
海外在住者の相続放棄については、当事務所の別サイトの下記記事をお読みください。
海外在住の相続人が相続放棄する際の流れや必要書類、注意点を解説
日本の相続手続き
日本で相続登記をする際は、さまざまな書類を揃える必要があります。
まず、誰が相続人であるかを証明するために戸籍謄本を必要なだけ一式揃えなければなりません。最近では、法務局で法定相続情報一覧図の交付を受けて銀行などの窓口で相続手続きを進めることもできますが、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには戸籍謄本類が一式必要なので、戸籍は必ず一度は集める必要があります。
また、銀行など金融機関の窓口で相続手続きをするときには、遺産分割協議書や金融機関所定の書類に実印を押して印鑑証明書を添付するのが一般的です。
さらに、不動産を相続して名義変更登記をするには、不動産を取得して名義人になる方の住民票が必要です。
相続人全員が日本国内にいても書類を全て揃えるのは大変ですが、相続人の中に海外在住の方がいる場合や、相続人が外国に帰化している場合は、必要な書類を揃えるのがさらに大変になります。
日本に一時帰国したときに相続手続きをやってしまいたいと考える方もいらっしゃいます。ただし、事情によっては、海外の居住国で揃える書類もあるので、日本に一時帰国している間に相続手続きを済ませたい場合、帰国前に準備をしておく方が良いこともあります。
海外在住の相続人が日本国籍の場合
海外に居住している日本国籍の相続人がいる場合、日本の役所で発行される印鑑証明書や住民票の代わりに、以下の書類が必要となります。
印鑑証明書に代えて署名証明書(サイン証明書)
遺産分割協議書など、相続手続きに必要な書類には実印の押印と印鑑証明書の添付が求められるのが一般的です。しかし、海外在住で日本の住民登録がない方は印鑑証明書を取得できません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わりになるものが「署名証明書(サイン証明書)」です。これは、申請者の署名(及び拇印)が本人のものであることを、海外にある日本の大使館・領事館(在外公館)が証明する書類です。
署名証明書は、領事の面前で署名(及び拇印)して、申請者本人により署名(及び拇印)が領事の面前でなされたことの証明です。
- 署名証明書の取得方法: 原則として、申請者本人が居住地を管轄する日本の在外公館に出向き、領事の面前で対象書類(例:遺産分割協議書)に署名する必要があります。代理人による申請は認められていません。
- 日本一時帰国中の代替: 日本に一時帰国している場合は、日本の公証役場で同様の認証(署名認証)を受けることも可能です。
住民票に代えて在留証明書
相続によって不動産を取得する場合、登記申請時に新しい所有者の住所を証明する書類として住民票が必要になります。海外在住で日本の住民票がない場合は、その代わりに居住国の日本領事館発行の「在留証明書」が必要となります。
- 取得方法: 署名証明書と同様に、原則として本人が居住地を管轄する日本の在外公館に出向いて申請します。
- 目的: 海外における現住所を公的に証明する書類です。
在外公館に行くのが困難な場合
在外公館から遠方にお住まいの場合や、高齢・病気などの理由で在外公館への行くのが難しいケースもあります。その場合の代替手段は次のとおりです。
- 署名証明書の代替: 不動産登記においては、居住国の公証人(Notary Publicなど)による署名証明書、日本に一時帰国中に日本の公証人による署名証明書が認められる場合があります。また、在外公館で印鑑証明書の交付を受けることもできるようです。
- 在留証明書の代替: 居住国の公証人の認証を受ける方法があります。
ただし、これらの代替手段が常に認められるとは限りません。手続きを進める前に、必ず当事務所のような専門家にご相談して確認してから取得してください。
海外在住の相続人が外国籍を取得している場合
海外在住の相続人が外国に帰化して外国籍を取得している(あるいは元々外国籍の)方がいることもあります。この場合には相続手続きはさらに複雑になります。
外国に帰化すると日本国籍を離脱して戸籍が無くなっているので、戸籍謄本以外の方法で相続人であることを証明する必要があります。また、ほとんどの国で印鑑証明書や住民票が出ないので、それらに代わる書類が必要です。もともと外国籍の方も同様です。
この場合、日本国籍でないため、現地の日本領事館で署名証明書や在留証明書を発給してもらうことはできません。聞いた話では、日本の在外公館で日本のパスポートや居住国に滞在できるビザの提示を求められ、それらを提示できないとその国の国籍を取っていると見られ、日本の在外公館で証明書の発給を断られるとのことです。
韓国や台湾のように、印鑑証明制度や住民登録制度、戸籍や家族登録の制度がある国の場合は、これらの証明書を取得して相続手続きに利用できます。ただし、完璧なものが揃うとは限らないので注意が必要です。
韓国や台湾以外の国では、別の対応が必要です。
日本の戸籍謄本がないため、相続人であることを証明するために、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など、本国の公的書類が必要になります。さらに、一般的には、必要事項を1通にまとめた宣誓供述書を作成し、これに現地の公証人の面前で署名し、認証を受けたものを利用するのが一般的です。宣誓供述書には、日本の相続手続きで証明したい内容を、日本の法務局や金融機関で受け付けられるように記載します。
専門家に相談したところ、その専門家が宣誓供述書の書き方がわからないから、どこかで作ってもらってから来るように言われたという問い合わせをされることがあります。しかし、どのような内容を記載するかは相続の内容がわからないと作れません。基本的に専門家の方からの問い合わせでしたら打ち合わせを進めながら対応可能ですが、一般の方が専門家から丸投げされたケースのお問い合わせは専門家から連絡をいただくようお願いしています。
外国語で作成された文書は、日本語への翻訳文が必要になります。外国の公文書にアポスティーユや領事認証は、日本国内での手続きでは、基本的に必要ありません。
海外在住相続人の必要書類 早わかり表
| 相続人の状況 | 日本での代替対象書類 | 必要となる主な代替書類 | 主な発行機関 |
| 海外在住の日本国籍者 | 印鑑証明書 | 署名証明書(サイン証明書) | 日本の在外公館 居住国の公証人 日本の公証人 |
| 海外在住の日本国籍者(不動産相続時) | 住民票 | 在留証明書 | 日本の在外公館 居住国の公証人 |
| 海外在住の外国籍者 | 印鑑証明書、住民票 | 宣誓供述書(Affidavit)+身分・住所・署名証明 | 居住国の公証人等 日本の領事 |
| 海外在住の外国籍者 | 戸籍謄本 | 出生証明書、婚姻証明書等 +宣誓供述書 | 居住国の発行機関・公証人 |
実務上の障壁:時間、コミュニケーション、国際送金
海外在住の相続人が関わる手続きには、特有の困難さが伴います。
時間的な制約
署名証明書や遺産分割協議書などの書類を海外の相続人と郵送でやり取りする場合、往復だけで数週間以上かかることも珍しくありません。相続登記の義務化(3年以内)や相続税申告(10ヶ月以内)の期限を考えると、迅速に進める必要があります。
また、書類取得のために在外公館へ出向く必要があり、予約や移動時間も考慮しなければなりません。日本人が多い地域では、予約がかなり先になってしまうといった例もありますので、早めの対応が必要になります。
コミュニケーションの問題
物理的な距離と時差:があるため、直接会って話すことが難しく、電話やオンライン会議を行うにも時差の調整が必要です。
また、相続財産の詳細や日本の法制度について、海外在住の方に正確に理解してもらうのが難しい場合があります。特に海外在住の方が財産の相続を望まない場合、相続手続きに非協力的ということも珍しくありません。こういった事情が遺産分割協議がスムーズに進まない原因にもなり得ます。
国際送金の難しさ
相続した預貯金や、不動産の売却代金を海外の相続人の口座に送金する場合、銀行での手続きに手間がかかります。マネーロンダリング防止の観点から、銀行の国際送金手続きが年々厳しくなっています。
国際送金をする際に、日本の銀行で送金の根拠となる書類を求められ、また海外で受け取る際にも証拠となる書面を求められることがあります。銀行での手続きがうまくできないと、一旦送金したお金が戻されてくることすらあります。
相続人の方が海外在住でも日本に銀行口座をお持ちの方もいらっしゃいます。そのような場合には、日本国内の銀行口座に振り込むこともできます。ただし、非居住者であることが銀行にわかると取引を制限されることがあり、場合によっては支店の窓口でないとお金を引き出せなくなることもありますので、注意が必要です。
海外在住の相続人が手続きを進めるとき
相続人の一部が海外在住の場合で、日本にいる相続人が手続きを進めることができれば、書類の収集等で時間がかかることはあっても、そんなに相続手続きで問題はないかもしれません。
しかし、相続人全員が海外在住の場合や日本にいる相続人が高齢や病気で相続手続きのために動けない場合で、海外在住の相続人が日本の相続手続きを進めなければならないときは、困難を伴います。
このような場合には、司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する方がスムーズに進むでしょう。当事務所では不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの相続手続き一式を遺産承継業務として行っています。
特に、相続人全員が海外在住で、今後日本に居住する可能性が無い場合には、日本国内の財産を換価処分して、金銭を相続人に海外送金することを希望されることが多いでしょう。当事務所では、遺産承継業務として引き受けた案件については、換価した遺産を海外の相続人に送金する手続きもしています。
日本にある相続財産を換金して海外に送金する場合、預貯金の解約は他の専門家でもできても、不動産の処分は簡単にはいきません。以前に、ある士業が預貯金のみ解約して全額を海外送金し、不動産は難しいからという理由で不動産の登記および処分を放置したために、固定資産税すら滞納になっているというケースがありました。
海外から相続手続きを日本の専門家に依頼する場合には、その専門家がどこまでやってくれるのかを確認してから依頼するようにしてください。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは相続人が海外在住の場合、次のようなサポートをいたします。
- 相続による不動産の名義変更登記申請
- 預貯金の解約
- 不動産の売却処分のサポート
- 遺産分割協議書の作成及び翻訳
- 宣誓供述書など認証を受けるための書類作成
- 海外在住の相続人との連絡事務
- 海外への送金事務
- 外国語文書の翻訳